
日清紡の貨物ホーム |

煉瓦積みの工場 |
|
|
|
|
|
さて西武鉄道の方は、川越線との交差地点手前では日清紡工場の前を通過。ここには何と本線のすぐ脇に貨物ホームが存在する。今では線路も取り払われてその役目は終えている様だが、現役の頃は側線が存在し、貨物が積み出されて行ったのだろう。工場裏手の方へとまわって行ってみると、夏休みで人けのない敷地内には、ひんやりとした煉瓦積みの重厚な建物が佇んでいた。

川越,東上線との立体交差 |

本川越駅構内 |

本川越駅前 |
|
|
|
|
|
川越線、東上線を潜ると、もう終点の本川越駅。ここは西武線がフラットで通過して行くのに対し、JRも東武もそれを跨線橋で乗り越している。川越鉄道が開通したのが明治28年、東上鉄道が大正3年、さらに国鉄の川越線が昭和15年だから、後から来た鉄道は先に出来ていた鉄道との立体交差を考慮する、という原則に則った作りだ。ただし、ギリギリまで高さをケチッたためか、あるいは電化を考慮していなかったのか、西武の電車はかなりパンタをすぼめさせられて、このガーダーの下を通過して行く。
本川越駅のホームは、開設当時もう少し奥まった所(すなわち街の中心部方向)にあったと思われるが、現在はだいぶJR側に寄せて作られている。その分空きとなった奥の方の土地には、駅ビルに続くショッピングセンターの大きな建物が続いている。そう言えば当初の「川越」の駅名も、その後省線の開通と共に川越線の方にとられてしまい、やむなく「本川越」を名乗って現在に至っているのだ。

電線のない空が広い |

顔を連想させる建物 |

ビルの装飾も凝っている |
|
|
|
|
|
とりあえず終着点にまでは達したが、せっかくここまで来たのだからと少し市内を流して行く事にする。駅からそのまま通りを北上すると、川越のメインストリートと言っていい風致地区に至る。ここは電線が地上から撤去されており、周囲の蔵作りやレトロなビル等の建物と調和した街並みを演出している。銀行、酒屋、土産物店...、どこもそれらの建物で実際に営業中なのが嬉しい。中に新しいコンビニのチェーン店が一軒あったが、周囲に配慮した日本風の外観になっているというのが、なかなかに心憎かった。
大通りを 2ブロックほど進んで左手の路地へと入り、しばらく行くとそこが有名な菓子屋横丁。ここ元町二丁目付近には、江戸時代からお菓子を作る店が軒を連ねていたという。現在はどちらかというと昔懐かしい駄菓子屋さん系だが、名物のイモ菓子等を作り売りしている店もある。ここで私は「焼いもアイス」と、おみやげ用に「むらさきいもキャラメル」の袋詰を購入。アイスは良くある最中でなくキャンデーバータイプのものだったが、なかなかあっさりした甘味で美味しかった。

時の鐘 - 私の手は合成デス(^^;) |
〜川越と舟運(しゅううん)〜
川越に集まる生産物や荷物は、幕末から明治初期にかけては新河岸川を使って江戸へと運ばれていた。新河岸川は川越の市街地から屈曲しつつ下流へと向かい、北区の岩淵水門で荒川と合流して隅田川となり都内へ至る。ここを多くの荷船や屋形船が貨客を運んで、早くは二日、最長で二十日程かかって一往復していたという。
その後日本鉄道が高崎線を開通させる時、当初川越を通過する設計だったのだが、川越町の有力者はこれに対し貨客を奪われるとの危機感を持ち、一定の株式を引き受ける代わりに町内の通過を避けてもらいたい旨、日本鉄道と談判に及んだそうだ。
結局日本鉄道は現在のルートに落ち着いたものの、その後川越鉄道が開通し、流通経路が大きく変わると共に舟運は大打撃を受けた。一部の回船業者は見切りをつけて、駅前の運送店として再出発を計った者もある。さらにこれに追い討ちをかけたのは東上鉄道で、新河岸川とほぼ同じルートで開通し、これにより舟運は衰退の一途をたどった。
この様にして舟運を主役の座から追いやった鉄道だが、貨物についてはその後のモータリゼーションにより、自動車に台頭されて久しいのはご承知の通りである。
|
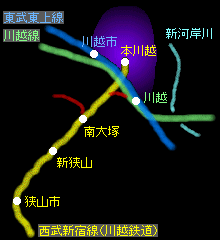 |
|
|
|
|
|
さてさてそろそろ帰ろうか、イャその前に大事なもの大事なもの...。大通りは幸町の酒屋さんで、地ビールを物色。小江戸ブルワリーの「さつまいもラガー」と「伝説のビール職人」を仕入れた。これにて川越鉄道の旅は、カンパーイ!じゃなかったカンリョー!!って事で。
参考:
- 「さいたまの鉄道」 埼玉県立博物館 編集
- 「トワイライトゾ〜ン MANUAL 7」 (株)ネコ・パブリッシング 発行
- 「多摩のあゆみ Vol.73」(特集:川越鉄道百年) たましん地域文化財団 発行
 Back to Rail Page
Back to Rail Page