14. 三ヶ島湿地
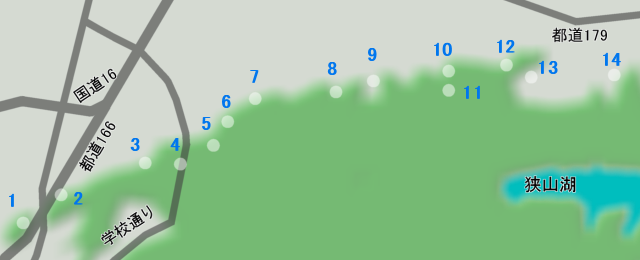
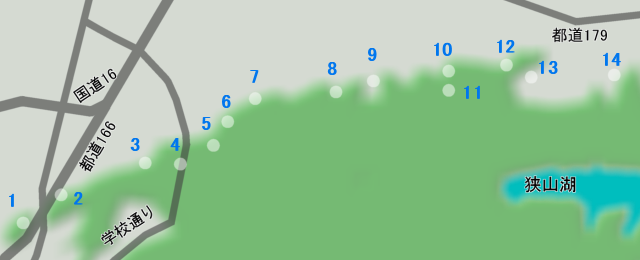

比良の丘を下って次の三ヶ島湿地へと向かう道。 ペダルを漕ぐ必要もなく、遠くの景色を眺めつつユルユルと坂を下って行くのは至福の時間だ。

途中でちょっとルートをミスったかなと気付いて停車した目の前に、こんな案内が立っていた。 左卜全(ひだりぼくぜん)氏と言えば「ずびずばー」の人であるが、このあたりの出身だったのか。 調べてみると本名「三ヶ島一郎」との事で、先祖は三ヶ島村の氷川神社神官であり、そこから分家した家系だそうだ。

正しいルートにリカバリーして坂下へ降り着き、折り返すように2度右折すれば、すぐこの景色が目の前に現れる。 ここがこの近辺で最大の谷戸と言える三ヶ島湿地の入口になるわけであるが、ご存じの通り、一帯は早稲田大学が購入した敷地となっており、一般の立ち入りは制限される。

地図によればこの奥にフロンティアリサーチセンターという施設がある。 車道中央にはゲートが設けられていて関係者以外の車は入れそうにないが、歩道には何も無く、徒歩で中の施設に向かう人には配慮されているようである。

そのゲート脇から歩道フェンスの外側を覗くと、谷戸の奥手方向へ至ると思われる木道が見えている。 ひょっとしてこちらは入って行けるのかも、と一瞬思ったが、入口に鍵がかかっているのでここも大学敷地の一部なのだろう。
そんな事を考えながらウロウロしていたら、施設の職員らしき人に声をかけられた。 これは不審者として怪しまれてしまったか?と一瞬心配したが、そうではなかった。 聞けばその方は大学でなくこの谷戸を保護管理している団体の職員で、私の来意を説明すると、三ヶ島湿地について色々と解説してくれた。

驚いたのはこの荒れた湿地の一番奥の方で、生態の研究目的ではあるが今も稲作が行なわれており、毎年収穫もあるという事実だ。 雑草で荒れるのを防ぐため、何年かごとに区画をずらして地面を耕し、稲を植えているそうである。 公開で観察会なども行なわれているようなので、ちょっと調べて、機会があれば参加してみたいと思っている。
三ヶ島湿地 の一言感想
次は、井上稲荷脇の谷戸に向かいます。